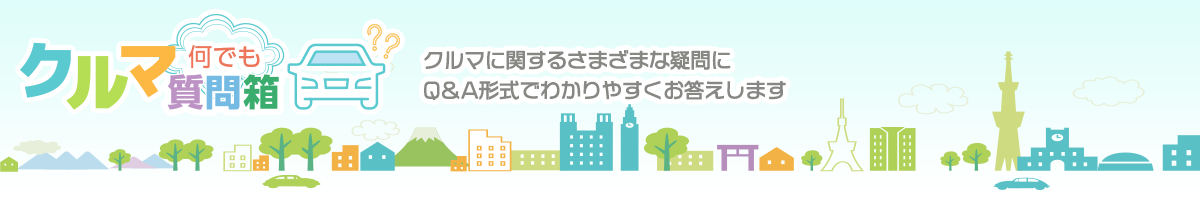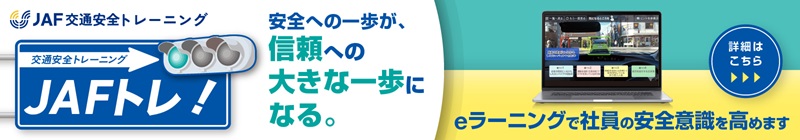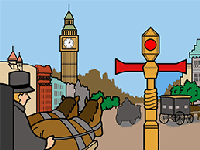
[A]CIE(国際照明委員会)によって、信号機は赤・緑・黄・白・青の5色と規定され、交通信号機には赤・黄・緑の3色が割り当てられているからです。
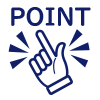
- 国際照明委員会の既定の色で、交通信号には赤/黄/緑が割当てられた。
- 日本初の自動交通信号機は1930年に設置され、中央柱式タイプだった。
- 赤信号が右にあるのは注意を促しやすく、街路樹に影響されないため。
見やすい色に決められました
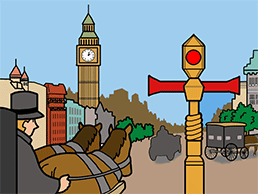
世界で最初の交通信号機(以下、信号機)は、イギリスのロンドン市内で馬車の交通整理のため、1868年にガス灯火式の信号機が設置されました。確かな記録は残っていませんが、このときの信号機は、使用する色も含めて鉄道の信号機を原型にしていたと考えられています。
電気式の信号機は、1918年にアメリカのニューヨーク5番街に設置されたものが世界初といわれています。このとき、すでに信号機の色は赤・黄・緑の3色が使われていました。注意喚起を主な目的とした黄は、赤と緑の中間にある色として採用され、雨や霧など視界が悪い中でも比較的良好に判別できることも、黄が使われた理由かもしれません。
なお、信号機の色は、海外でも日本と同じ赤・黄・緑の3色が使われています。これはCIE(国際照明委員会)によって、信号機は赤・緑・黄・白・青の5色と規定され、交通信号機には赤・黄・緑の3色が割り当てられているからです。そして、ほぼすべての国で信号機の「止まれ」には赤、前に「進んでも良い」には緑が使われています。
緑なのに青信号と呼ぶのはなぜ?
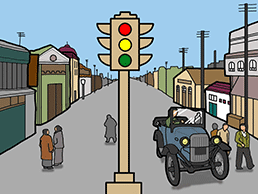
日本で最初の自動交通信号機は、1930年3月、東京の日比谷交差点に設置されました。アメリカ製の信号機で、灯器を交差点の中央に置く「中央柱式」と呼ばれるタイプでした。しかし、当時は「進メ」「止レ」などと書かれた標識を手動で操作する、あるいは警官が挙手の合図で交通整理を行うのが普通でした。そのため色による信号機はなかなか理解されず、広く浸透するまでには相当な時間がかかったといわれています。
道路交通法では第2条で信号機について、電気により操作され、灯火により交通整理などのための信号を表示する装置と定義されています。そして第4条では、交通安全や障害防止などのために都道府県公安委員会が必要と認めたとき、設置および管理ができると定めています。さらに第7条では、道路を通行する歩行者や車両は、信号機や警察官の手信号などに従わなければならないとあります。
日本では「緑」信号を「青」信号と呼んでいます。信号機の3色は赤・黄・青と表現されることが多く、免許の更新時に配布される交通教本にも、「青色の灯火は進むことができる」と記載されています。
自動信号機が導入された当初は、海外に倣って赤・黄・緑の3色として認識されましたが、第二次世界大戦後の1947年に制定された道路交通取締法第3条では青色としてあり、現在の道路交通法施行令も第3条で青色と記しています。
緑を青と呼ぶ理由は、日本語の「青」が表す範囲の広さにあるようです。青菜、青竹、青葉など緑色のものを青と呼ぶ場合が多かったため、緑信号を青信号と表現するようになったようです。また、赤の対極にある色が緑ではなく青だからという説、色の三原色である赤・黄・青が影響しているという説もあります。
信号機で赤が一番右側にある理由とは?
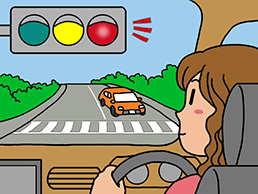
交差点に設置されている一般的な横型の信号機は、左から青・黄・赤と色の順番が決められています。道路交通法施行令第3条でも、右から赤色、黄色及び青色の順と記してあります。これは信号機で重要な色の赤を道路の端から中央寄りに置くことで、ドライバーに見やすくするのが主な目的です。一般的にはドライバーが右側に座っているので、赤信号も右側にあったほうがより注意を促しやすくなります。もし街路樹の枝が伸びて信号機にかかり灯火が見づらくなっても、赤信号の右側は影響されにくい場所でもあります。
また降雪量の多い地方では、雪が信号機に積もらないように縦型を採用することがあります。このタイプも、見やすさを考慮して赤が一番上になっており、前述の道路交通法施行令にも定めています。このように信号機は、数々の工夫を組み込みながら交通整理としての役割を果たしています。
2023年08月現在