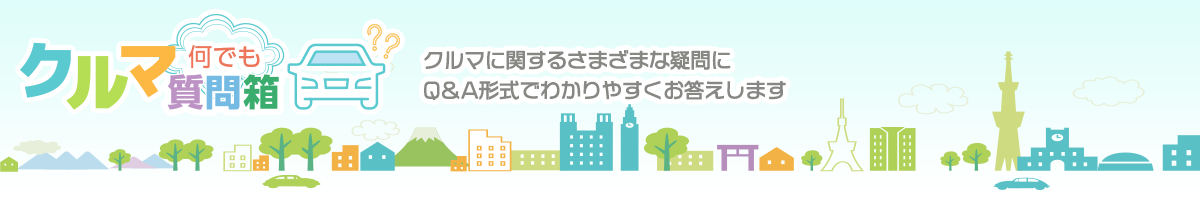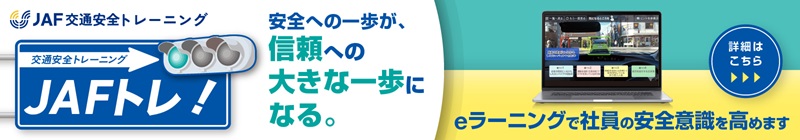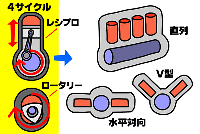
[A]クルマのカタログに記載されているエンジンの種類は、主に冷却方式とシリンダーの配置、バルブやカムシャフトの数や位置の違いによって分類されています。
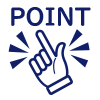
- エンジンの冷却は、現在の四輪車はほぼすべてが水冷方式を採用。
- シリンダーの配置による分類には、直列、V型、水平対向などがある。
- ハイブリッド車はモーターの種類についても記載される。
現在は水冷の4サイクルレシプロエンジンが主流
クルマのカタログに記載されているエンジンの種類は、主に冷却方式とシリンダーの配置、バルブやカムシャフトの数や位置の違いによって分類されています。
まず冷却方式は、二輪車では空冷方式の車種もありますが、四輪車ではほぼすべて水冷方式になっています。クーラントと呼ばれる冷却水でエンジンを冷やし、そのクーラントをラジエーターで冷却するという仕組みで、ラジエーターに冷却ファンが装備されていることもあり、エンジン本体の温度変化を抑え、安定した環境性能や動力性能を発揮できることが長所です。
エンジンの仕組みとしては現在、シリンダー内でのピストンの往復運動を回転運動に変換するレシプロエンジンが主流ですが、内部でローターが回転し動力を取り出すロータリーエンジンも存在します。レシプロエンジンは、燃焼行程により2サイクルと4サイクルに分かれており、現在のクルマは1回の燃焼を4行程で行う4サイクルとなっています。
シリンダーの配置による分類では、直列、V型、水平対向などがあります。直列エンジンは、直列4気筒などのように、シリンダーが一直線に並んでいるタイプのものです。ロータリーエンジンも直列になります。V型エンジンはシリンダーを左右交互に振り分けて配置したもので、エンジン本体の長さを抑えられるため多気筒エンジンに向いています。水平対向エンジンは、クランクシャフトをはさんで左右に向かい合うようにシリンダーを配したタイプで、エンジン本体の幅は広くなるものの重心が低くなるというメリットがあります。
OHV、SOHC、DOHCの違いは?
ガソリンとディーゼルという分類もありますが、エンジンの種類に記されることはなく、使用燃料のところにガソリンあるいは軽油という記述をするのが一般的です。ディーゼルは使用する燃料が軽油になるほか、燃焼方法も違います。低回転から粘り強いトルクが得られ、燃費も良いことから、トラックやバスでは主流です。以前はヨーロッパを中心に乗用車でも普及していましたが、近年は厳格化する排出ガスをクリアするために車両価格が上昇しているうえに、電気自動車やハイブリッド車の普及もあって、シェアを減らしつつあります。
そしてガソリン、ディーゼルに限らず、4サイクルエンジンではバルブやカムシャフトの数や位置によって、OHV(オーバー・ヘッド・バルブ)、SOHC(シングル・オーバー・ヘッド・カムシャフト)とDOHC(ダブル・オーバー・ヘッド・カムシャフト)に分けることができます。OHVは以前はシリンダーの横にあったバルブを上に移動させることで燃焼効率を高めたもの、SOHCはカムシャフトも上に配置し、バルブとの距離を近づけて高回転化を可能としたもの、DOHCは吸気バルブと排気バルブを駆動するカムシャフトを分けたもので、燃焼室の設計が自在になり、高性能や低燃費の追求に有利になります。
なおターボチャージャーなど過給機付きエンジンの場合は、過給機の種類が書かれていることもあります。またハイブリッド車の場合はモーターの種類が、交流同期電動機などと記されており、電気自動車の場合はエンジン関連の記述はなく、モーターの種類のみの表記になっています。
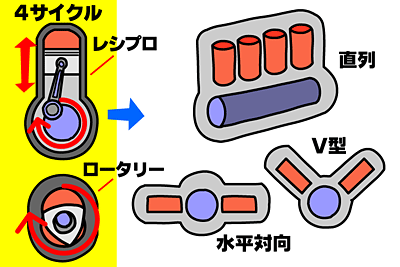
2025年11月現在